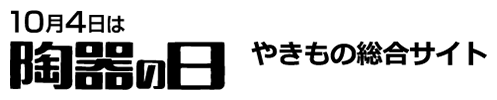器=銹絵五寸皿(田端志音)
写真:津留崎徹花 撮影協力:加島美術
二言目には「個性」「自分らしさ」を強調する学校教育の行き過ぎか、現代の陶芸の世界で、「写しもの」の旗色はあまりよくない。だが名作を生み出した先達を理解し、その先へ進むために既存の作品を「写す」ことは、かつて日本では当たり前の文化だった。陶芸家の田端さんもやはり古典に魅了され、その魅力を自らのものにしようと努力してきた一人。古美術商での勤務を経て、田端さんが作陶を始めたのは45歳の時。遅いスタートだったからこそ、田端さんは多岐にわたる技法を使いこなし、器形のバリエーションも豊富な17世紀の陶工・尾形乾山を「師」に選んだ。粘土から釉薬、窯に至るまで、可能な限り乾山時代と同じ技法を再現するために試行錯誤を重ね、現在では錚々たる日本料理店でその作品が使われる、名うての「乾山写し」として知られる。乾山が生きた時代、こうして柿の菓子を食べたとしても不思議ではない、そんな取り合わせになった。